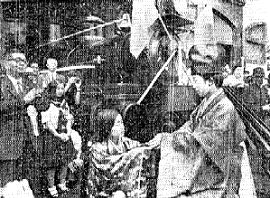|
 |
 七月の小樽 |
源平合戦の英雄である源義経が、兄の頼朝にほろぼされたことは、よく知られていよう。義経は京都の朝廷に接近し、頼朝への抵抗をはかるが、そのもくろみは失敗した。追われる身となり、しばらくは奥州平泉にかくまわれる。しかし、頼朝を恐れる平泉の藤原泰衡におそわれ、衣川の高館で自害した。 その義経に、延命説がある。平泉では死ななかった。自害と見せかけ、その場は脱走する。 北の青森へにげのびた。海をこえ、北海道までわたっている。いや、それどころではない。大陸まで逃走し、再興をはたしている。金国の某将軍は義経だ。清朝の愛新覚羅家は、義経がルーツになっている。モンゴルのジンギスカンこそ、義経その人にほかならない、等々と。 これらの諸説が、いつどのようにしてできたのかは、だいたいわかっている。北海道までおちのびたと言われだしたのは、一七世紀後半の江戸初期であった。金や清との関連説は、一八世紀にうかんでくる。ジンギスカンに付会されだしたのは、一九世紀から。有名になったのは、二〇世紀の一九二〇年代以降である。 (井上章一「妄想かもしれない日本の歴史」) つまり、その時々の国策(アイヌ政策〜北海道開拓〜大陸侵略)に合わせて、義経の最長不倒は伸びて行くということですね。「妄想かもしれない日本の歴史」、「日本に古代はあったのか」を大真面目で追求してゆく井上章一の筆致が大好きで、なにか書き物に行き詰まった時などは、布団に寝ころんでよく井上さんの本をひろげます。(井上ひさしより役に立つ…) あるいは、和人によるアイヌ同化政策の一端を、義経伝説もになっていたのかもしれない。 そういえば、明治初期の北海道では、義経号、弁慶号、静号と名付けられた汽車がはしっていた。ここにも、義経をダシにした文化政策のにおいが、感じとれないではない。 最近、ちりぢりばらばらになっていた義経号と静号が、小樽で合流したと聞いた。鉄道ファンは、けっこうよろこんでいたらしい。私なんかは、同化政策のいやらしさをこえて、いい話だなと思うのだが。 で、これが、その「北海道百年」式典で配られていた記念切符。 |

| 義経号と静号 手宮〜札幌間に、わが国で第3番目に鉄道が開通したのが明治13年(1880)11月28日。機関車は米国ポーター社製モーガル型で、この年に輸入された第1号には“義経”、第2号には“弁慶”、次いで17年(1884)までに“比羅夫”“光圀”“信広”“静”など、本道にゆかりのある歴史上の人物の名がつけられたのである。 本道開拓当初に貢献した、これらの機関車は、その後民間に払いさげられ、長年使われていたが国鉄はその後、義経主従3両を原型に復し、日本鉄道初期の貴重な記念物として指定した。 “義経は”は神戸市の鷹取工場に、“弁慶”は東京の交通博物館に、“静”は国鉄苗穂工場に保管されていたが、現在は本市の北海道鉄道記念館に移されている。 “静”が初めて通ったときは、唯一の女性名の機関車なので、特に美しく装飾されていたという。 明治18年(1885)の冬、大雪で“義経”と“弁慶”が張碓トンネル付近で立往生したとき“静”は主君の一大事とばかり駆けつけ、これを救い出したというエピソードも伝えられている。 ともあれ、開道百年の記念すべき年に“義経”が、はるばる津軽海峡を渡って“静”と対面の場をもつことは、まことに意義深いことである。 (記念切符/裏面の解説) 開道百年。和人たちの勝利宣言に、また義経が津軽の海を渡ってきた。 去リやらぬ人がき 「義経」と「しづか」の対面 “世紀の対面劇”をひと目、記憶にとどめようと、正午ごろから勤めを終えたサラリーマンや親子連れが続々とつめかけ「義経」の前は黒山の人がき。線路上にアマチュアカメラマンかいっぱい。消防本部音楽隊の前奏マーチか始まったころ、いまにも泣き出しそうだった曇り空から小雨がパラついてきた。武将義経が白拍子の静を見染めたのも雨やどりのときだったそう。この雨も「しづか」の再会のうれし涙みたいだ、と関係者。 午後一時、マーチがとまると、駅長姿に身を固めた稲垣視聴が出発の合図。蒸気をはき出し、ぬれた車体を武者ぶるいさせた「義縫」が、“出陣”。ゆるやかにチャイムを響かせてのデモンストレーション。観客のカサもそれにつれて動いた。 一時半かっきり、手宮西小児童約百人のかわいらしい鼓笛隊に迎えられて「しづか」の前に到着。本道では四十五年ぶりだが、“二人”がゆかりの深い小樽でこんな形で対面するとは考えられなかったという(小熊米雄・道鉄道友の会長の話)。一千人を越える鈴なりの観客のなかで、筑波踊り会の少女二人がふんした義経、静が越天楽の調べにのって再会のあいさつをかわすと、五十羽のハトが放たれ再会を祝福した。 (北海道新聞 昭和43年7月21日 小樽版) 盛り上がってますね。記事に二人の写真があったので、記念に一枚。 |