五月から始まる啄木カレンダー
デジタル篇
明治四十丁未歳日誌 (1907年)
(「啄木勉強ノート」HPより引用)
 明治40.10.15 小樽日報初号発刊
明治40.10.15 小樽日報初号発刊
一天朗らかに晴れて風なく、心気爽々たり、
小樽日報初号発刊の日、
正午の頃に至りて刷上れり、凡て十八頁、楽隊を先立てゝ市中の配達は景気よく終れり、
午后五時より社主中村定三郎氏より招待されて一同静養軒に祝宴を張る。七時半、職工一同楽隊と共に提灯行列を初め、静養軒前に来て万歳を連呼す、我等飛び出して共に提灯ふりかざし市中を練り歩げり市中の景気大によし、
わが妻に着物縫はせし友ありし
冬早く来る
植民地かな
(一握の砂「忘れがたき人人」)
 明治40年10月15日
明治40年10月15日
祝!小樽日報創刊
というわけで、本日の小樽の歌も、私のいちばん好きな「わが妻に…」の歌をかけました。
(小樽日報社)
この歌、10年前に小樽に来てから知った歌なのですけれど、毎年この季節になると「しんとして幅広き街の/秋の夜の/玉蜀黍(たうもろこし)の焼くるにほひよ」といっしょに口をついてよく出てきます。人生の応援歌ですかね…小樽と札幌。札幌の応援歌だけはもうひとつあって、それは、宮沢賢治の「札幌市」という詩。(今、「おたるの青空」に掲載中) いずれの歌も北国の街をシャープに捉え、かつ、その街のさえざえとした気温までが伝わってくるような歌です。
野口雨情と「樺太」の続きです。
野口雨情のことを調べて行くと、いかに私たちは「啄木」側から物事を見ることに慣れきっているのかに気がつきます。例えば、「啄木、野口雨情との出会い」。
普通、私たちは啄木年譜に出てくる「野口雨情」しか気にとめませんから、「ああ、札幌の北門新聞社時代に同業の野口雨情を知ったのね…ふたりで示し合わせて小樽日報社にデューダしたんだろう…」といった理解になります。でも、ちがうんですよ。みんながみんな、啄木みたいに都会で食いつめたり失敗したから単純に北に流れてきたような人ばかりではないのです。
明治15年(1882)5月29日に茨城県で生まれた雨情が東京専門学校高等予科文学科に入学したのは同34年だが、翌35年春に「小柴舟」や「小天地」に新体詩を発表して詩壇に出た。二十歳のときで、同時に東京専門学校を中退しているが、雨情がはじめて北海道に渡ったのはこの年という。
(『樺太文学の旅』より「野口雨情の北緯五十度行」)
東京専門学校は、現在の早稲田大学ですか。この、初めての北海道も、明治35年6月の雑誌「少国民」に発表された『密漁船』や同年9月の『砂金採』といった作品を読む限りでは、かなり奥深い北海道侵入…という印象を受けます。
神の教への夕暮れは雲ゆ映れる星の色
寂しき北のオコックにおぞむの海の日は落ちぬ (「密漁船」より)
父はと問へば北なる空を指して
石狩川の山中に砂金採りぢゃと答へたり (「砂金採」より)
 野口雨情という人は、「何故あなたはそこにいるのか?」という問いには、なにか答えようのない人としていつも「そこ」にいるんですね。これが、金田一京助だったら「アイヌ語の採集のため」、ジョン・バチュラー博士だったら「キリスト教の伝道」とか(たとえ本人の意識は別のところにあったとしても)一般大衆の納得用に看板みたいな存在理由をとりあえずは設置するもんなんですけどね。なんか、野口雨情って、そういう計らいが全くない。底抜けに壊れているような気がするのです。同類の啄木以上に。
野口雨情という人は、「何故あなたはそこにいるのか?」という問いには、なにか答えようのない人としていつも「そこ」にいるんですね。これが、金田一京助だったら「アイヌ語の採集のため」、ジョン・バチュラー博士だったら「キリスト教の伝道」とか(たとえ本人の意識は別のところにあったとしても)一般大衆の納得用に看板みたいな存在理由をとりあえずは設置するもんなんですけどね。なんか、野口雨情って、そういう計らいが全くない。底抜けに壊れているような気がするのです。同類の啄木以上に。
この北海道を切り上げて故郷に帰るのが明治37年。(2年近く北海道をさまよっていたんだ…) 家督を継ぎ、結婚もし、子どもも生まれる。同38年には処女詩集『枯草』も出版。普通ならこの段階で落ち着いて都会の文士稼業に収まって行くものなのでしょうが、雨情は全然そうならない。翌39年、ついに(前回述べた)あの「樺太行」に突入してしまうのです!妻子を故郷に残して…
「三十九年七月頃、飄然として単身、北海道小樽港から樺太(現・サガレン)へ渡り、北緯五十度線にあたる西海岸の村アモベツにまで達した。『風は西吹く』(ハガキ文学 明39.8)をはじめ、この時期の傑作である『五十里』(新古文林 明39.11)などを発表しながら詩作の旅を続け、十一月に離島。やがて上京して新宿区西大久保に居を定め、詩作に没頭した」
この樺太行から帰ってくるのが11月。冬の間を東京で「詩作に没頭」。で、久しぶりの社会復帰というか、外に向かって動き出したのが翌明治40年7月、札幌の北鳴新聞社への就職でした。この時、野口雨情、25歳。7月に北鳴。でも、9月に啄木と知り合い、10月1日の小樽日報の編集会議には名を連ねているという具合で、その腰の落ちつかなさは相当なものです。で、10月31日には、あの有名な
野口君遂に退社す。主筆に売られたるなり。 (啄木日記)
ですからね。なんという人生の展開なのだろう。
この時期だけに限って言えば、野口雨情の「不気味さ」のスケールの方が啄木を勝っているように思えます。ヤクザに喩えるなら、これからひと仕事なにか手柄を立てなければ格好がつかない若造と、もうすでに最初の刑務所勤めを果たして組に戻ってきた若頭くらいのちがいがある。
雨情の「不気味さ」の特徴は、まずは、その動きの突飛さ、派手さです。大学を中退したと思ったら、突如北海道へ…とか。妻子を捨てて、突如樺太へ…とか。そして、その派手さをひとまわり大きく印象づけるのが、その「理由のなさ」なんです。なぜ小樽日報に鞍替えしたのか…、私たちは全然理由がわからない。その小樽日報を今度はなんともあっさりクビになる…、これも啄木が「主筆に売られたるなり」と解釈しているだけなのであって、雨情自身からは何の弁明もないんですね。ふいに小樽から消える。これは、とても不気味な事態です。真相を残さない…という技は。(そういう視点で今一度『赤い靴』という歌のことを考えるんですけど、いや、なかなか怖い歌ですね。)
もう「不条理」という言葉を使った方がいいのかな。
短い、つかの間のすれ違いだった啄木と雨情の人生。でも、啄木は、ここで「雨情」的な何かを学んでいるように思えます。歌のダイナミック・レンジが確かに拡がった。そして、その代償だったのでしょうか、散文能力が空中分解したようにも感じる。もう堅気(かたぎ)の世界には戻れない刺青か。
それにしても、みんな若かった!みんな、これから何者かに変貌して行く。
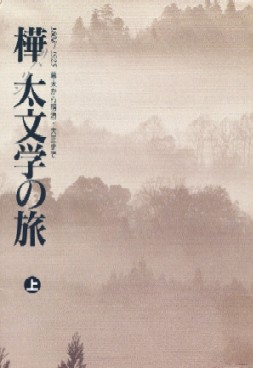 石川一(はじめ)が「啄木」へと変質し始めていた明治40年の夏、若干25歳の青年、金田一京助は樺太東岸のオチョポッカにありました。その一年前の明治39年夏になると、もっと凄い。野口雨情は、例の北緯50度線近い日露国境。この時、雨情24歳。他にも、柳田国男が中部の鈴谷高原から西海岸の真岡にまわっている。志賀重昂が樺太国境画定会議委員として小樽−樺太を往復。樺太への入り方も、間宮海峡を遡り北樺太のアレキサンドロフスク(歴山)港から横断・南下してくるといった面白い経路を辿っています。でも、いちばんの驚きは長与義郎(そう、白樺派の長与義郎!)でしょうね。なんと学習院中学校の修学旅行!この時、長与義郎、18歳。学習院中等科の五年生…
石川一(はじめ)が「啄木」へと変質し始めていた明治40年の夏、若干25歳の青年、金田一京助は樺太東岸のオチョポッカにありました。その一年前の明治39年夏になると、もっと凄い。野口雨情は、例の北緯50度線近い日露国境。この時、雨情24歳。他にも、柳田国男が中部の鈴谷高原から西海岸の真岡にまわっている。志賀重昂が樺太国境画定会議委員として小樽−樺太を往復。樺太への入り方も、間宮海峡を遡り北樺太のアレキサンドロフスク(歴山)港から横断・南下してくるといった面白い経路を辿っています。でも、いちばんの驚きは長与義郎(そう、白樺派の長与義郎!)でしょうね。なんと学習院中学校の修学旅行!この時、長与義郎、18歳。学習院中等科の五年生…
明治の人って度胸ありますね。あんまり面白いので、木原直彦著『樺太文学の旅』話題、もう少し続けます。
次回は「10月16日」
啄木、小樽の街へ…
カレンダー価値の減却により、9月からの「啄木カレンダー」は400円の定価になります。さっさとカレンダー部分を取り外して単純な「啄木絵葉書」で売れば…というご意見もあったのですが、考えた末、スワン社独立の「2003年」を心に刻んで生きて行くことにしました。カレンダーは役に立たなくとも、啄木が小樽にやってきた九月は、永遠に九月だ…と想いきめることにしました。<新谷>
|
五月から始まる啄木カレンダー 短歌篇 日記篇
表/カレンダー,裏/ハガキ仕様 各12枚組
プラスチック・ケース(スタンド式)入り



 野口雨情という人は、「何故あなたはそこにいるのか?」という問いには、なにか答えようのない人としていつも「そこ」にいるんですね。これが、金田一京助だったら「アイヌ語の採集のため」、ジョン・バチュラー博士だったら「キリスト教の伝道」とか(たとえ本人の意識は別のところにあったとしても)一般大衆の納得用に看板みたいな存在理由をとりあえずは設置するもんなんですけどね。なんか、野口雨情って、そういう計らいが全くない。底抜けに壊れているような気がするのです。同類の啄木以上に。
野口雨情という人は、「何故あなたはそこにいるのか?」という問いには、なにか答えようのない人としていつも「そこ」にいるんですね。これが、金田一京助だったら「アイヌ語の採集のため」、ジョン・バチュラー博士だったら「キリスト教の伝道」とか(たとえ本人の意識は別のところにあったとしても)一般大衆の納得用に看板みたいな存在理由をとりあえずは設置するもんなんですけどね。なんか、野口雨情って、そういう計らいが全くない。底抜けに壊れているような気がするのです。同類の啄木以上に。
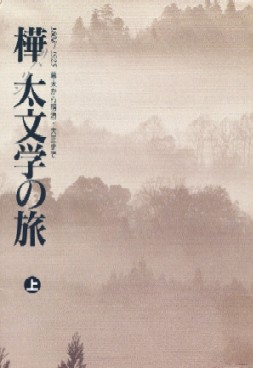 石川一(はじめ)が「啄木」へと変質し始めていた明治40年の夏、若干25歳の青年、金田一京助は樺太東岸のオチョポッカにありました。その一年前の明治39年夏になると、もっと凄い。野口雨情は、例の北緯50度線近い日露国境。この時、雨情24歳。他にも、柳田国男が中部の鈴谷高原から西海岸の真岡にまわっている。志賀重昂が樺太国境画定会議委員として小樽−樺太を往復。樺太への入り方も、間宮海峡を遡り北樺太のアレキサンドロフスク(歴山)港から横断・南下してくるといった面白い経路を辿っています。でも、いちばんの驚きは長与義郎(そう、白樺派の長与義郎!)でしょうね。なんと学習院中学校の修学旅行!この時、長与義郎、18歳。学習院中等科の五年生…
石川一(はじめ)が「啄木」へと変質し始めていた明治40年の夏、若干25歳の青年、金田一京助は樺太東岸のオチョポッカにありました。その一年前の明治39年夏になると、もっと凄い。野口雨情は、例の北緯50度線近い日露国境。この時、雨情24歳。他にも、柳田国男が中部の鈴谷高原から西海岸の真岡にまわっている。志賀重昂が樺太国境画定会議委員として小樽−樺太を往復。樺太への入り方も、間宮海峡を遡り北樺太のアレキサンドロフスク(歴山)港から横断・南下してくるといった面白い経路を辿っています。でも、いちばんの驚きは長与義郎(そう、白樺派の長与義郎!)でしょうね。なんと学習院中学校の修学旅行!この時、長与義郎、18歳。学習院中等科の五年生…
